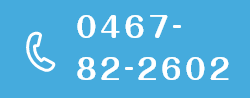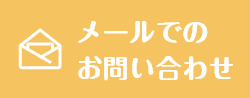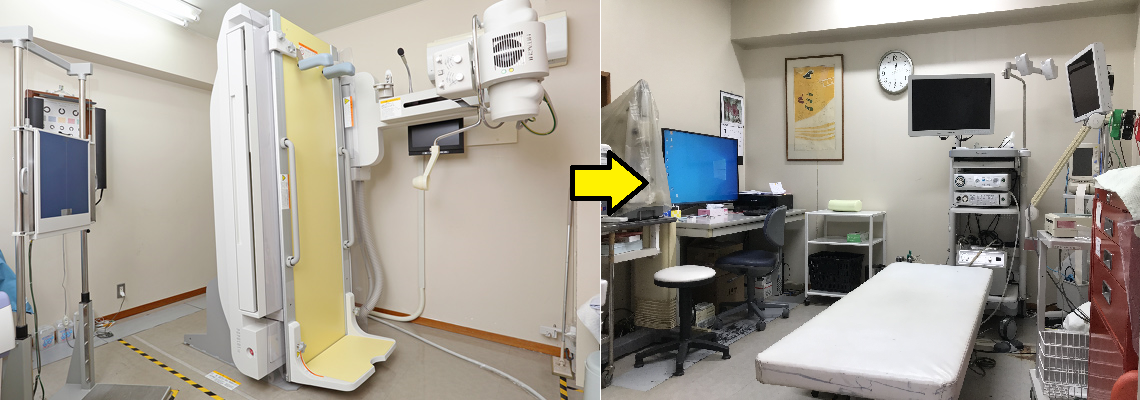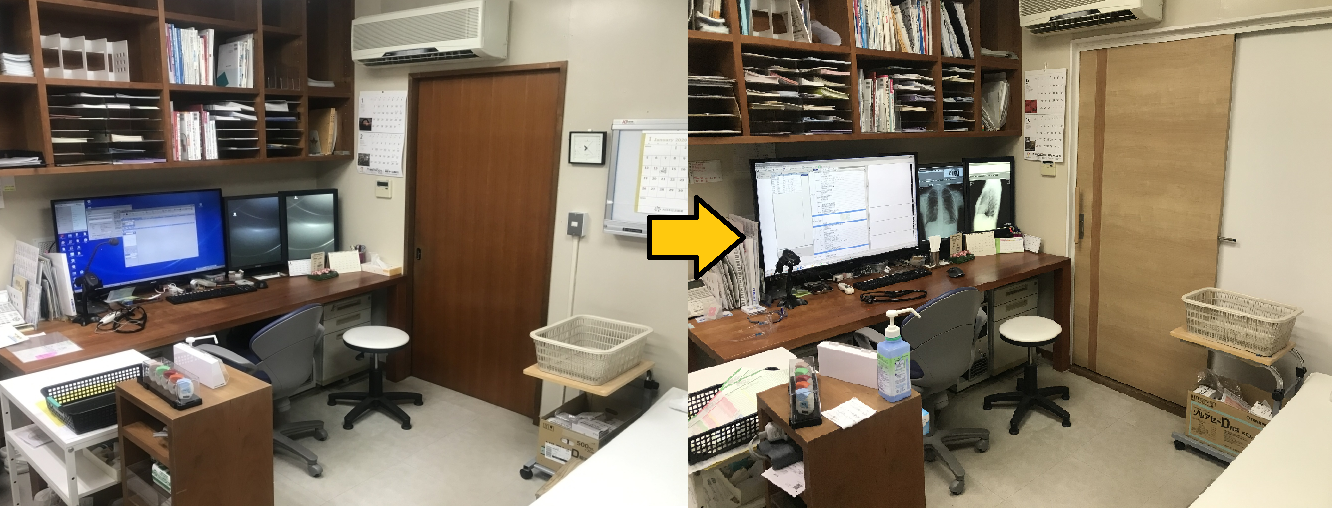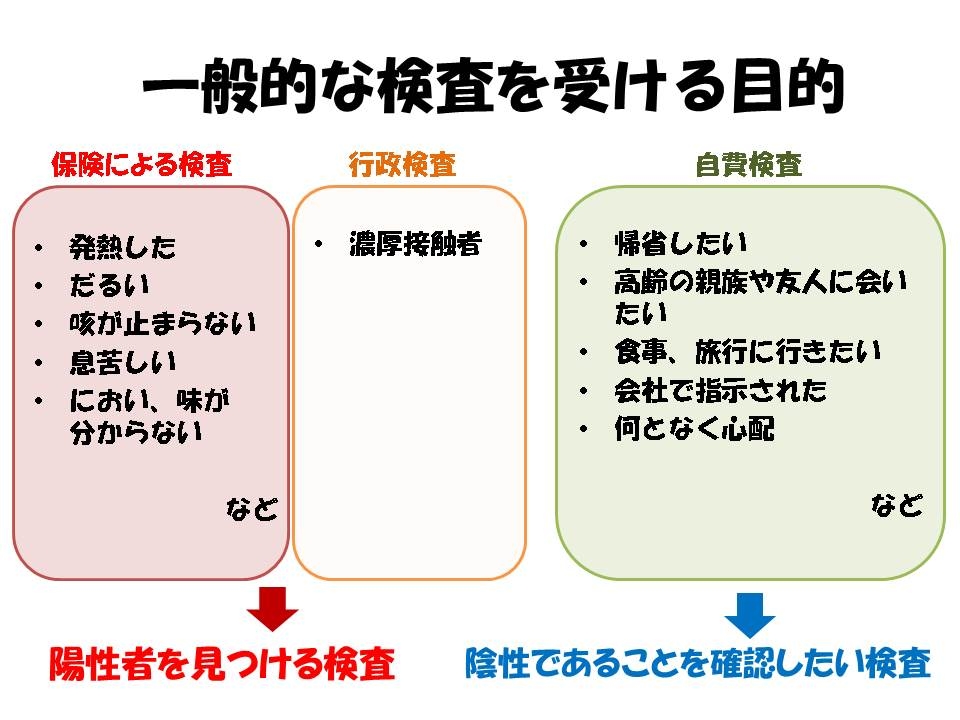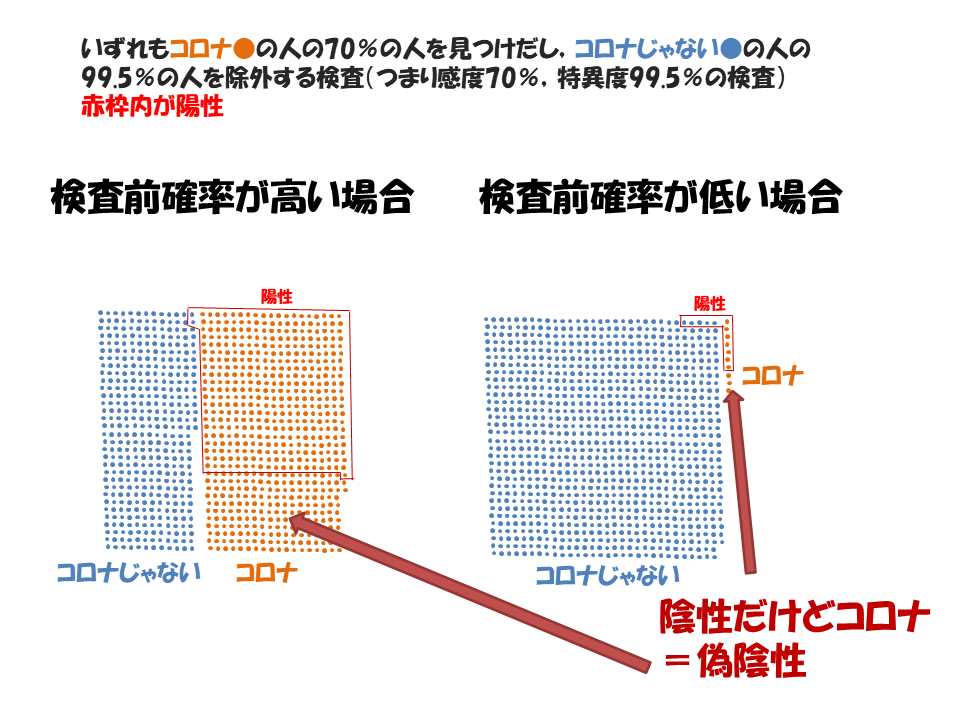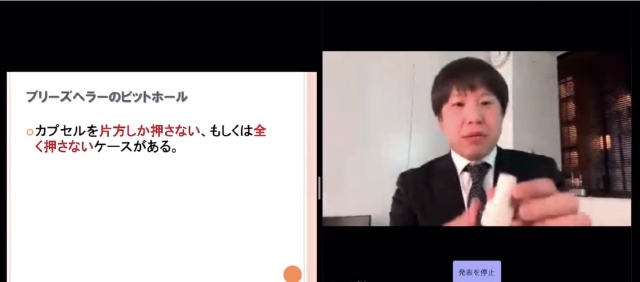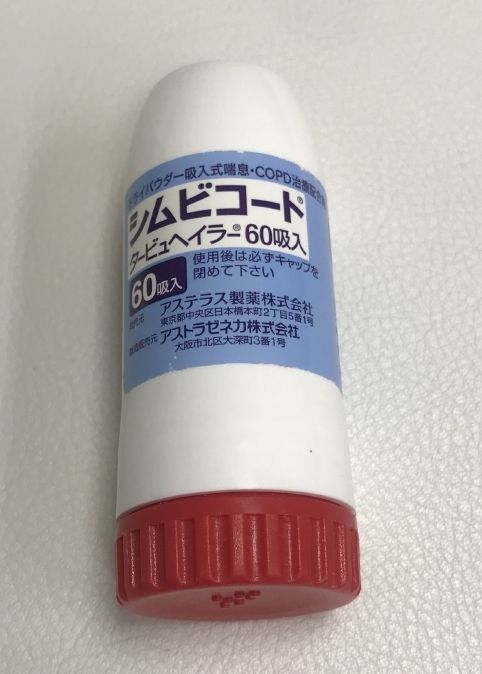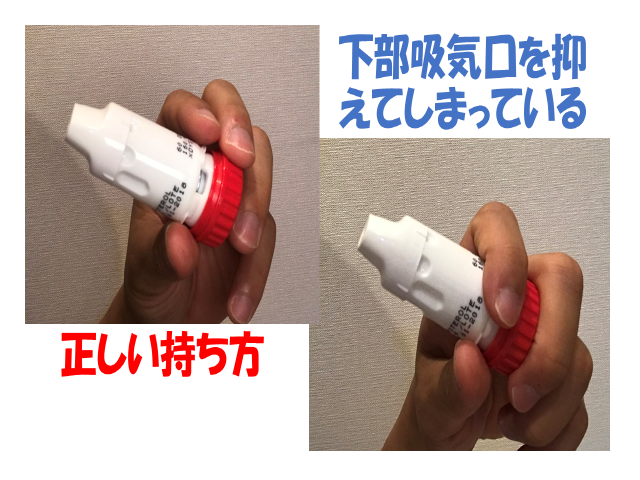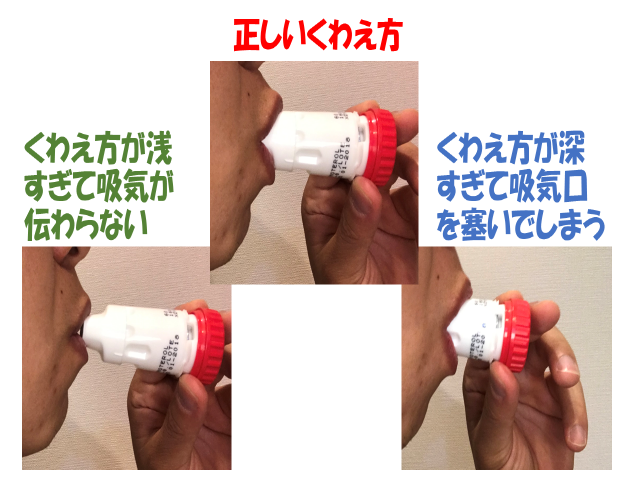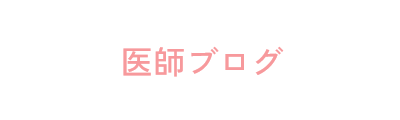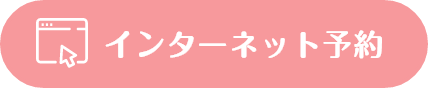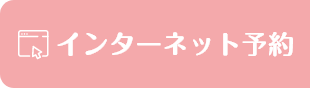ややコロナも山を越えてきたのでしょうか。
日々報じられる感染者数も一時期よりは少なくなってきました。
当院でも冬なので発熱や咳で来られる患者さんは相変わらず多いのですが、コロナを強く疑う患者さんの数は減ったように思います。また当院で実際にコロナと診断される患者も、年明けに比べればだいぶ減ってきているようであり、現場の実感としても落ち着きつつあるのかなという印象はあります。
しかし、コロナはやはり重症化が怖い病気です。
新規感染者の数が減ってもまだまだ重症者の数は多いようで、感染が判明してしばらく経ってから重症化するというコロナの恐ろしい面が反映されています。
このコロナに関しては、呼吸困難の自覚のないまま呼吸状態が悪化する「幸せな低酸素血症」“happy hypoxia”という状態が起こることが知られており、感染からしばらく経った後、気づいたときにはかなり呼吸状態が悪くなっていることがあるようです。
この原因としてはまだはっきりとは解明されていませんが、コロナが悪化しやすい高齢者や糖尿病の方は、もともと呼吸調節を行う調節機能が落ちている、呼吸困難を感じる体内のセンサー(頸動脈小体)にコロナウイルスが感染しやすく、そこのセンサーの機能が落ちることで呼吸困難を感じにくくなる、などの理由が考えられているようです。Martin J Tobin, et al. Why COVID-19 Silent Hypoxemia Is Baffling to Physicians. Am J Respir Crit Care Med. 2020;202:356-60.
現在軽症感染者さんの主な療養場所も自宅やホテルとなっており、ただの風邪症状の方もコロナである可能性が否定できない以上、家でも早期に呼吸状態の悪化を見落とさないようにする必要があると思われます。
そこで最近注目されているのがパルスオキシメータです(当院も今後の診療能力向上のために、今年からちょっとイイやつを新たに導入しました)。
これは日本語で「経皮的動脈血酸素飽和度測定器」といって、皮膚の上から光を当て、動脈血の「赤み」を測定する機械です(ちなみにこの機械が開発されたのは日本なんです!)。
使い方は、クリップになっている部分を開き、指を挟み、爪の部分が発光部にあたるように奥まで差し込むだけです。

血液が赤いのは、赤血球に含まれている「ヘモグロビン」という色素のためです。このヘモグロビンは酸素とくっつく性質を持っています。
肺で取り込んだ酸素は、肺に流れこんでくる血液の中のヘモグロビンとくっついて心臓に戻り、そして全身へと運ばれます(血液の液体の中にも溶け込みますが、溶け込んだ酸素はほぼ組織には運ばれず、液体の中にただよったままです)。
このヘモグロビン、酸素とくっつくと赤くなり、酸素から離れると黒くなるという性質を持っています。
すると、肺で酸素をため込み心臓から飛び出したばかりの新鮮な血液(つまり動脈血)は色が赤々としていますが、全身に酸素を配り終えた後の血液(つまり静脈血)は黒めの色となります。
皆さんが血液検査で血を採られると、意外に血が黒いと思われる人が多いですが、これはすでに全身に血液を配り終えた静脈血を採取しているからです。
そして、パルスオキシメータは先ほどお話ししたように動脈血の赤みを測定するため、肺から酸素をしっかり取り込めているかを測ることができるというわけです。
パルスオキシメータで測る数値を、動脈血酸素飽和度(SpO2)と呼びます。
これは血中のヘモグロビンのうち、何%のヘモグロビンが酸素と結合しているかを示しています。ですので最大値は100%になります。
そして血液中に含まれている酸素(これを酸素分圧と呼びます)と、酸素飽和度(SpO2)の関係は以下のグラフのようになります(これを酸素解離曲線と呼びます)。
上の表でもわかる通り、通常若い方の血液中の酸素分圧は95mmHg程度で、これは酸素飽和度(SpO2)でいうと98%に相当します。
また高齢者では酸素分圧80mmHg程度で、これはSpO2 95%に相当します。
機械の誤差を含め、95~99%であればあまり大きな問題はありません(100%だと時によっては過呼吸など、呼吸が多すぎることを疑います)。
そして、我々医師は通常、肺や心臓に慢性的な病気がない方の場合、SpO2が93%程度になると焦り始め、90%を切ると慌てます。これは酸素分圧60mmHgに相当し、これを下回ると呼吸不全とされます。
グラフもここを下回ると急になり、急激にSpO2が低下していき、いろんな臓器が十分な酸素を受け取れなくなってくるため危険な状態へとなっていきます。通常の場合では呼吸不全、つまり酸素分圧60mmHg、つまりSpO2 90%を下回る場合には、酸素療法や、場合によっては人工呼吸器療法によって酸素分圧を上げる必要がでてきます。
この治療の目安が指に機械を挟むだけでわかってしまうのです。
というわけで、痛みなく簡単に体内の酸素の状態が分かってしまうスゴい機械、パルスオキシメータですが、使うには実はいろいろな注意点があり、使用を安易に考えると、時に問題を生じることが出てきます。長くなりそうなのでこの続きはまた次回。
追記:続編はいつ出すんだ!?というご指摘を受け・・・
続編はこちらになります