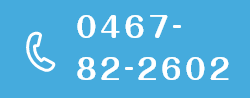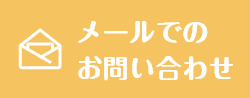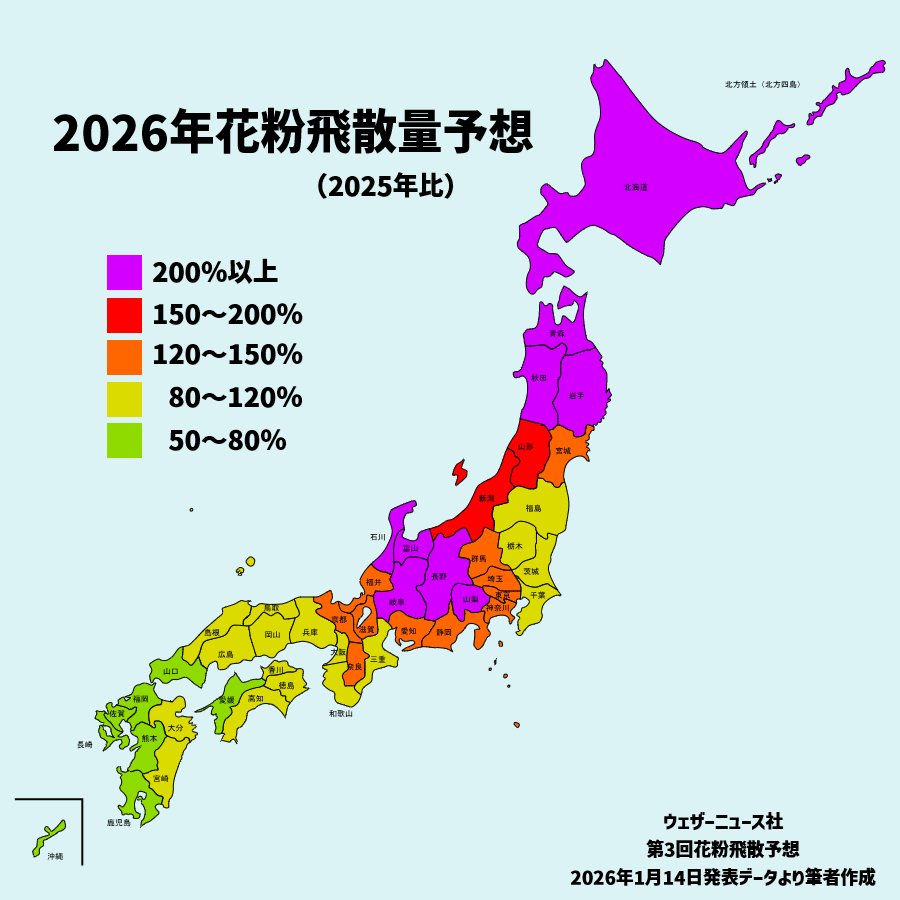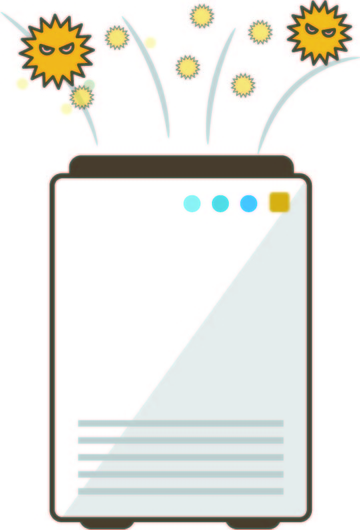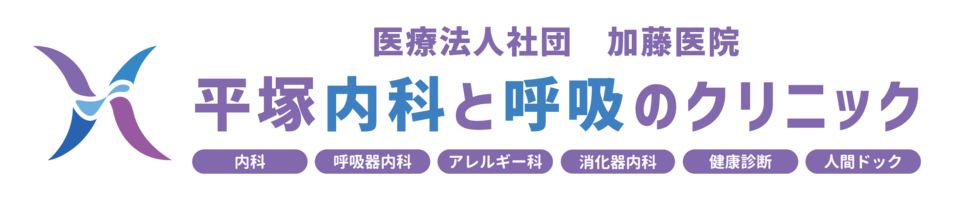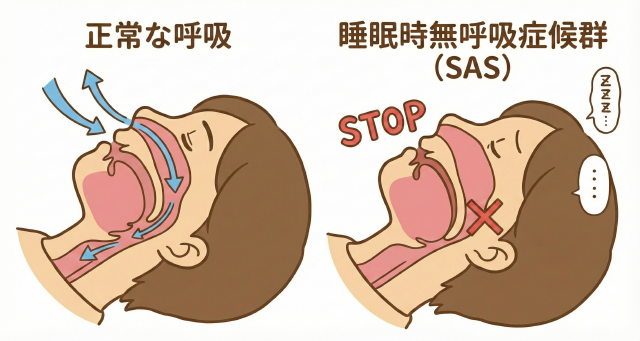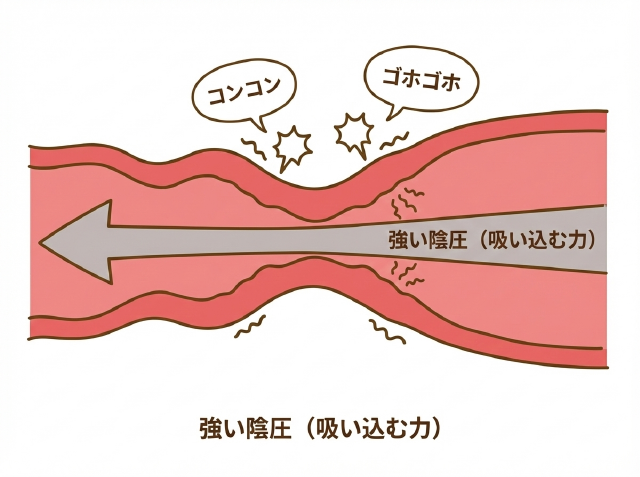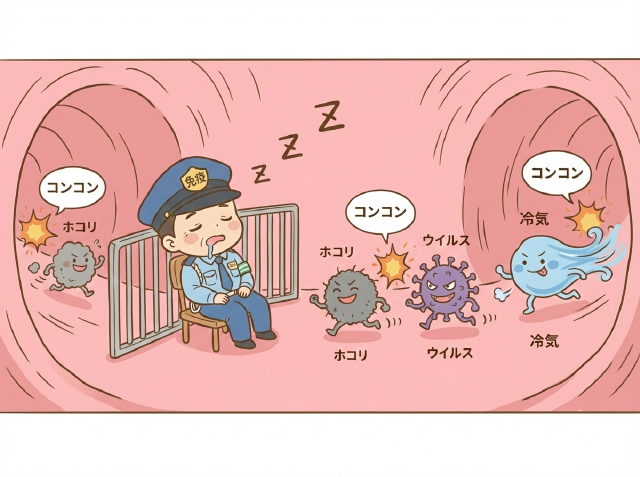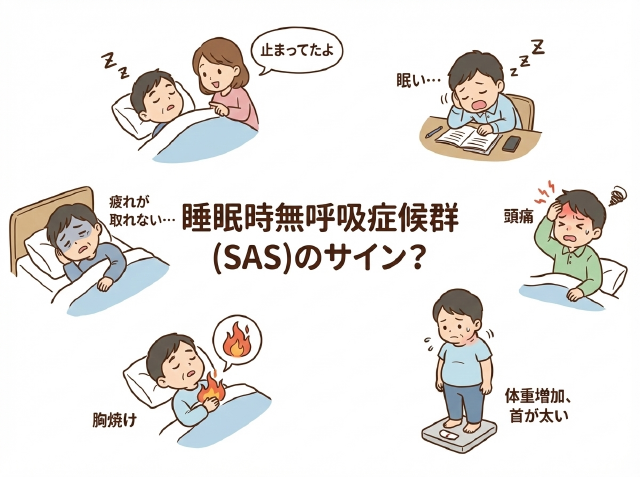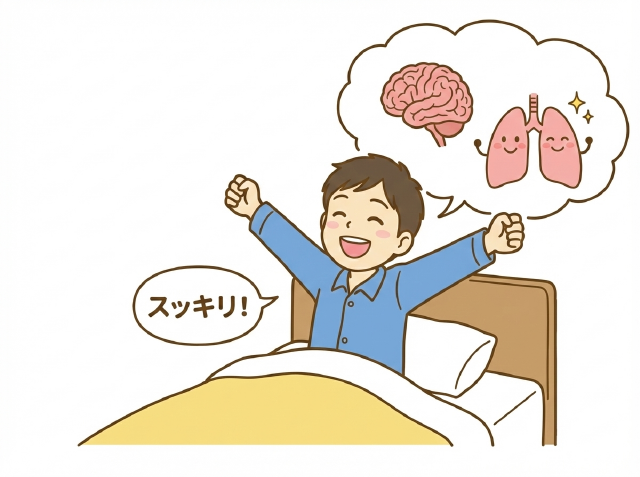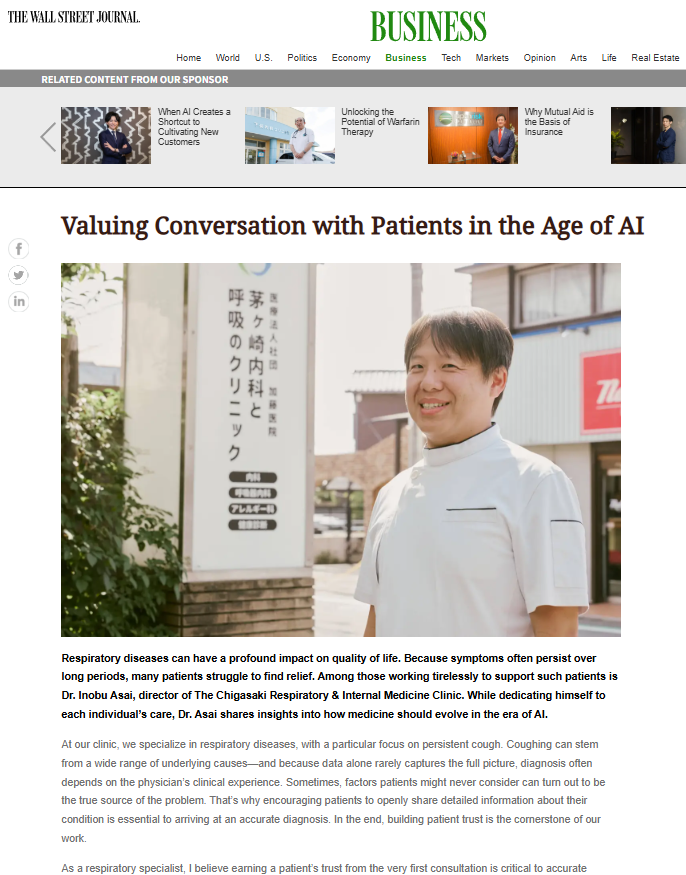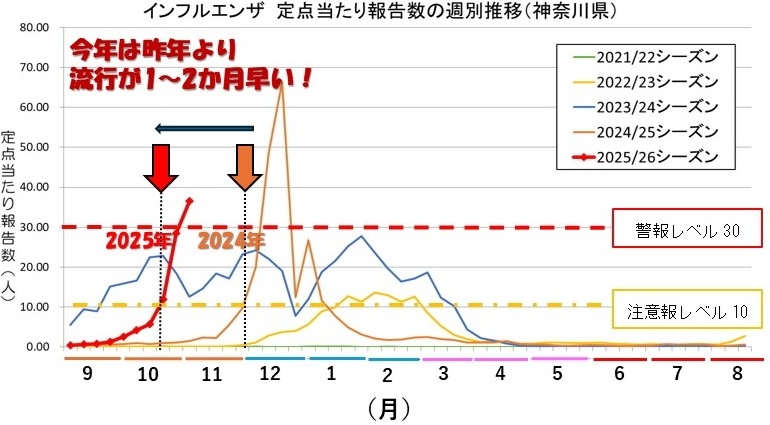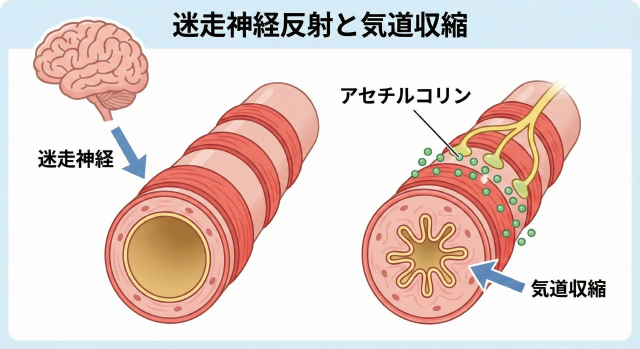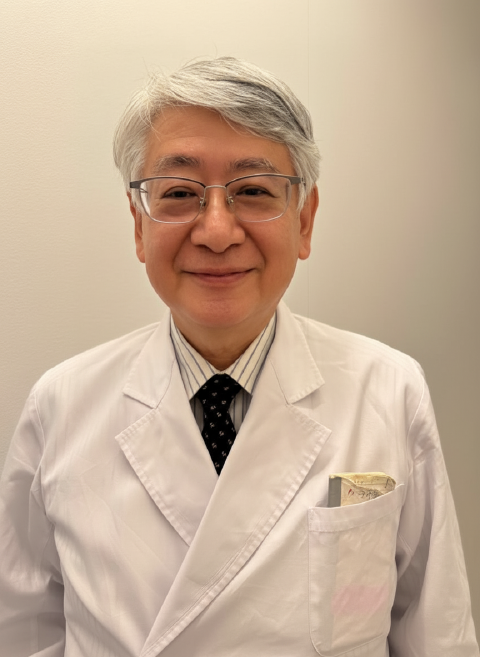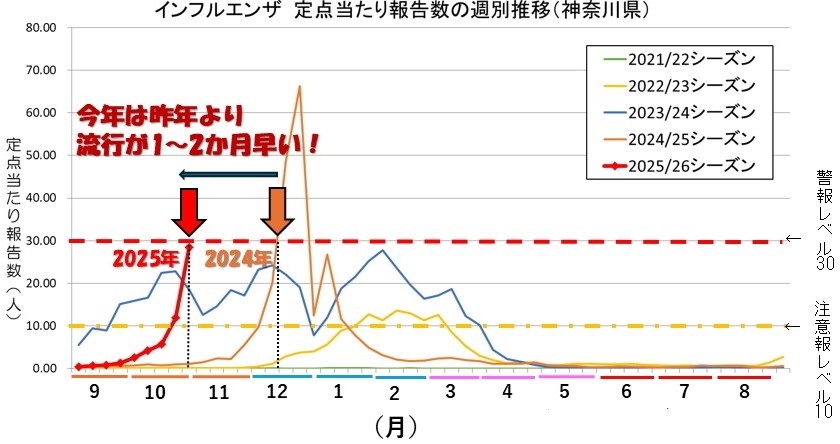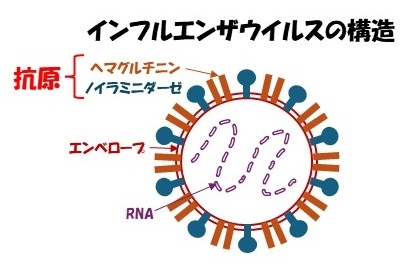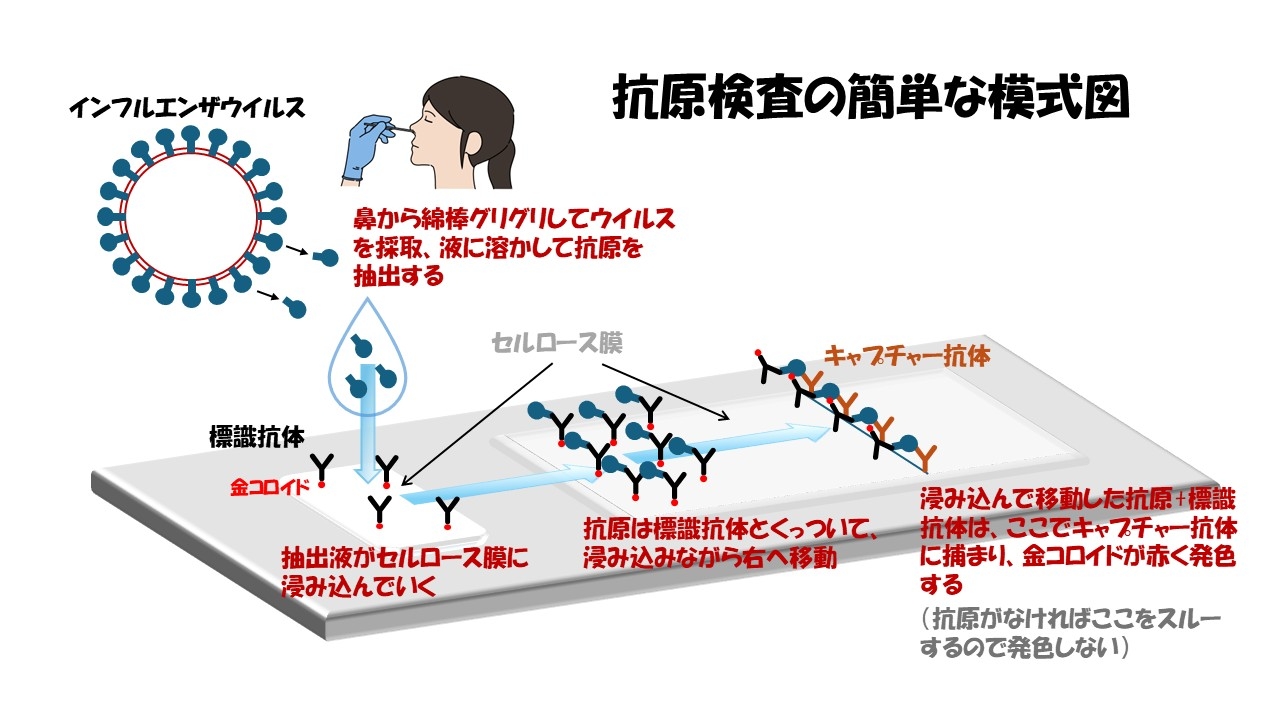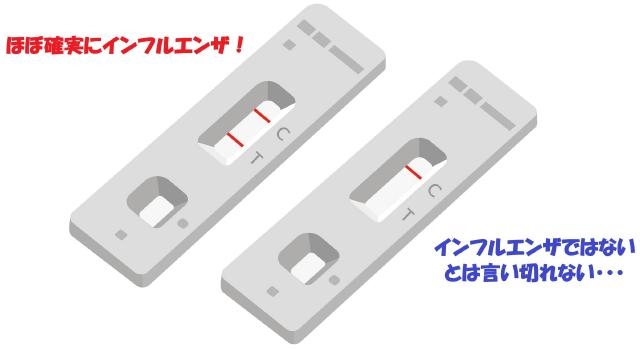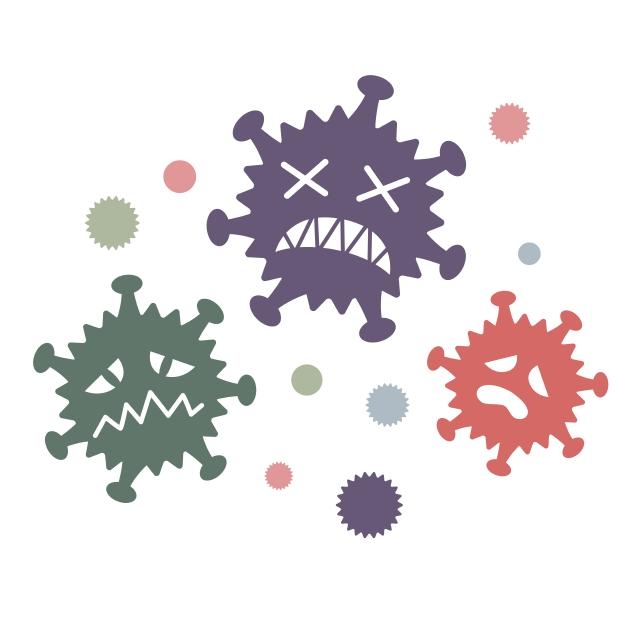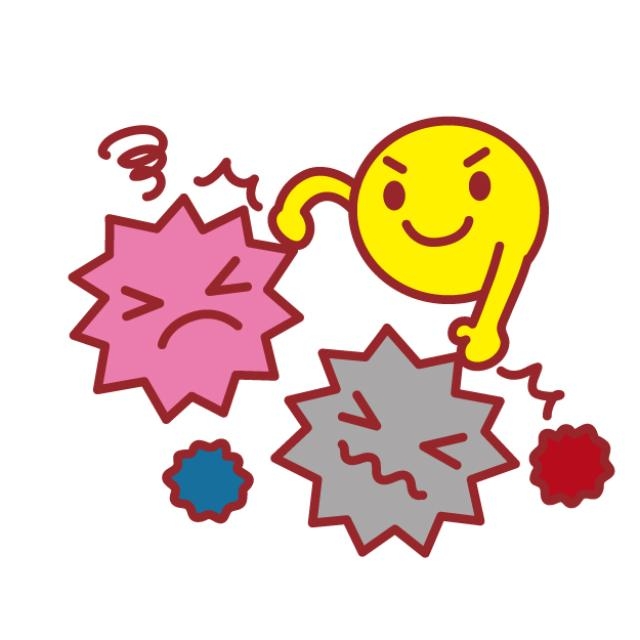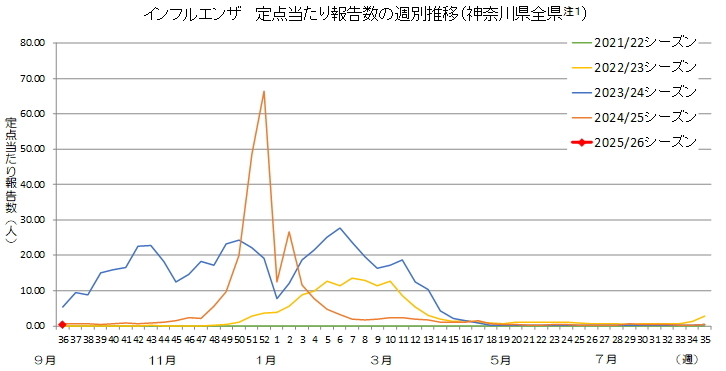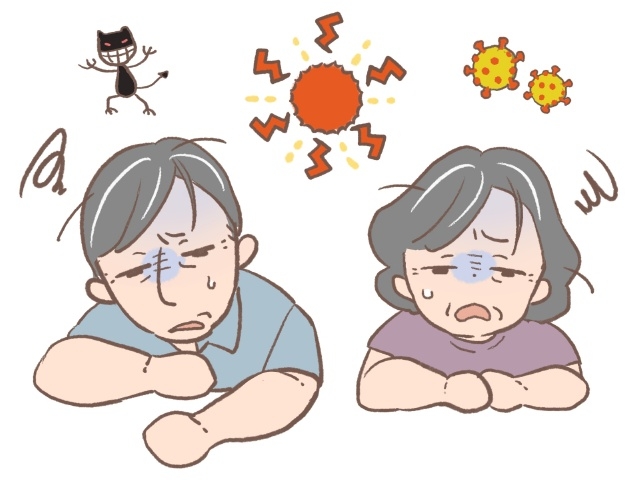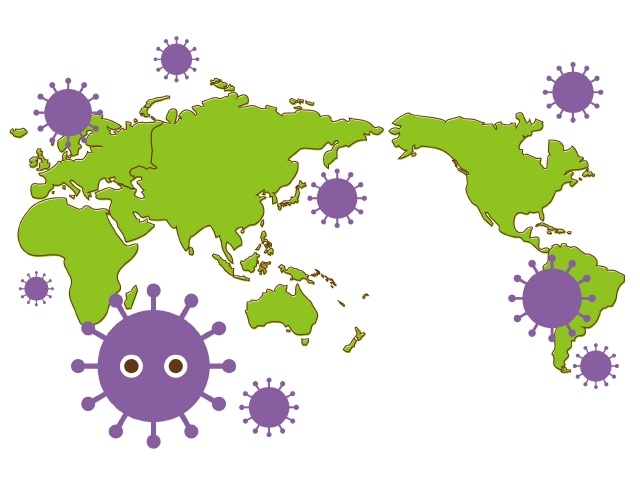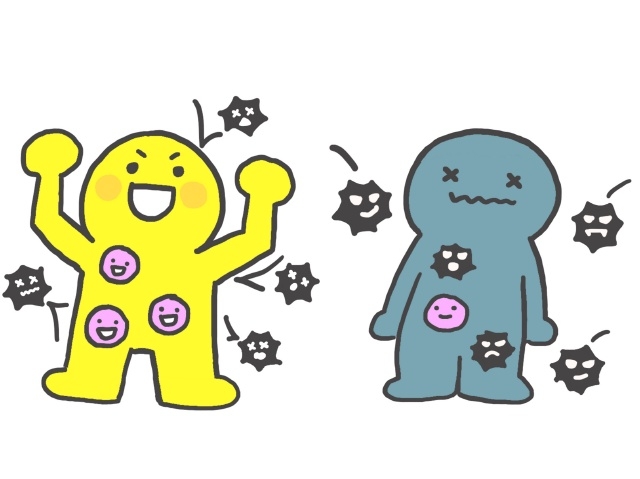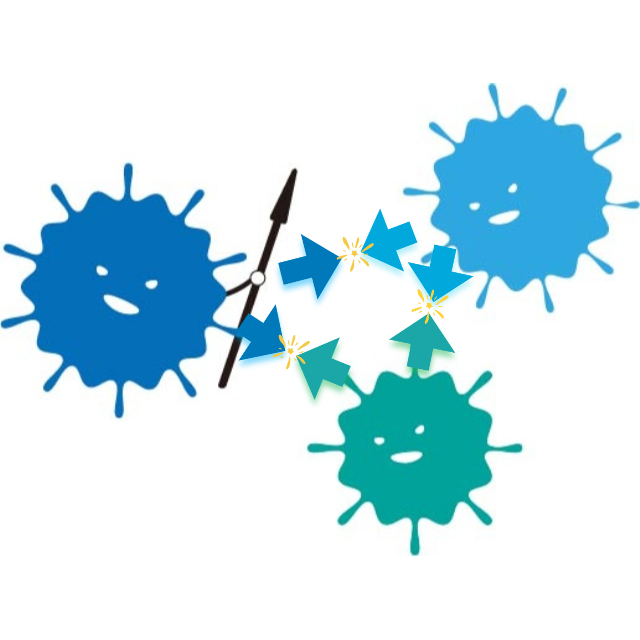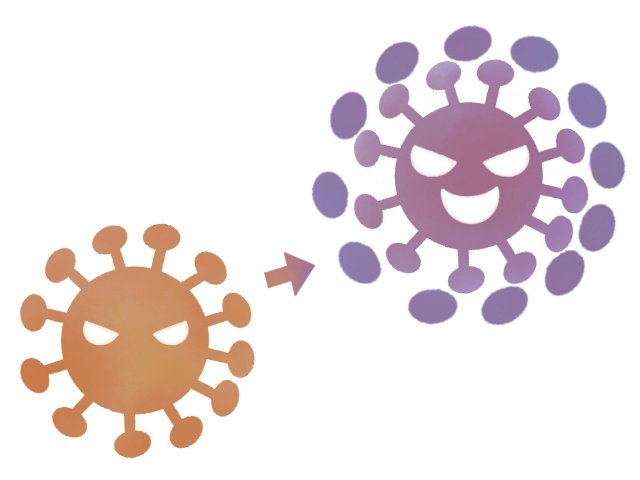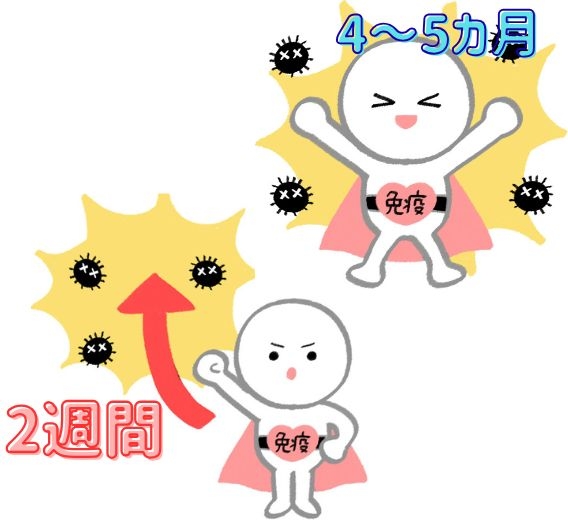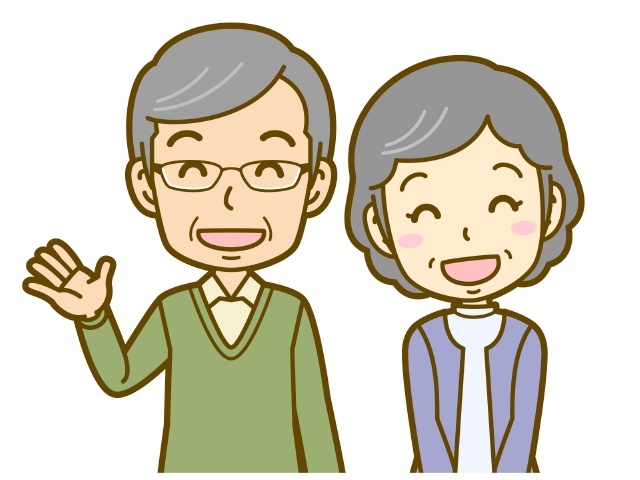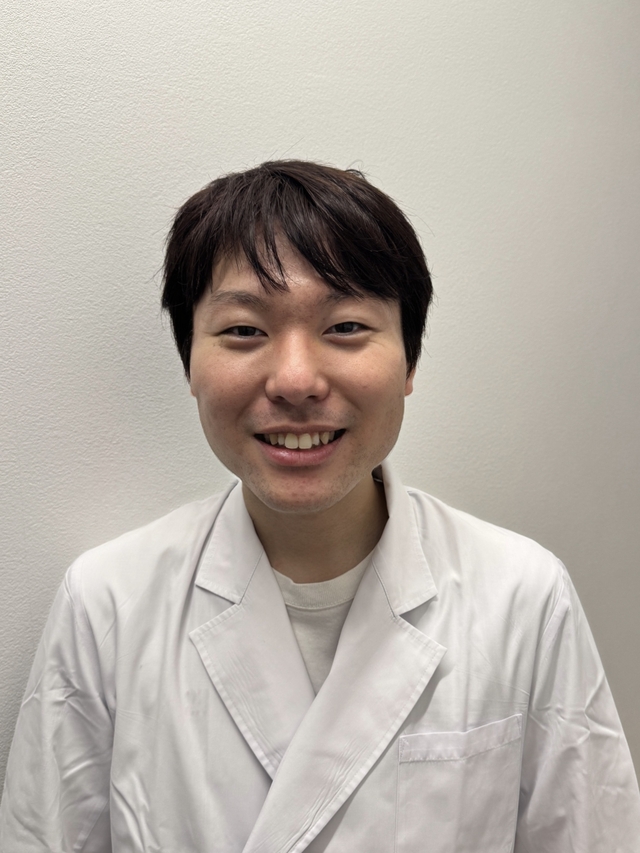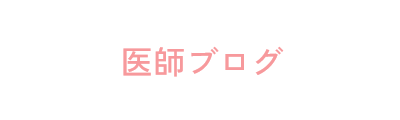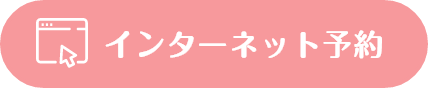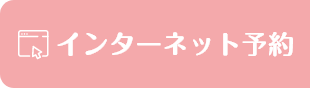「平塚内科と呼吸のクリニック」のオープンまで、2ヵ月を切りました。
「平塚内科と呼吸のクリニック」のオープン場所については、実は契約上2か月前にならないと明かしてはいけない(ただし「駅ビル」という表現はOK)約束だったのですが、この度開院2ヵ月前を過ぎ、正式にオープン場所をお伝えできることになりました。
「平塚内科と呼吸のクリニック」は、ラスカ平塚2階、「ラスカ平塚ドクターズスクエア」内にオープンします!
具体的には、平塚駅東口の改札を出て、右手側のラスカ平塚入口から3階に入り、「カルディ」さんの横を通った先のエスカレーターから2階に降りた「倉式珈琲店」さんのおとなりになります。

改札から歩いてみたら、99歩でクリニック前に到着しました!(ちなみに茅ヶ崎本院は改札から480歩でした・・・)
現在、平塚院は順調に建設が進んでいます。
今は壁も全てでき、クリニックのカタチがはっきりと浮かび上がっています。
今後はいよいよ壁紙、床と進んで、建設も終盤に差し掛かってきます。
平塚院の事務長となるO崎を中心に、ハイペースで建設報告ブログ「平塚建築日記」をアップしています(すでに本日で13本目です)。
ぜひこちらもご覧ください!
そして平塚院は2月末までに竣工し、皆様にお披露目できるのは
3月28日、29日
の内覧会となる予定です。
普段はなかなか見ることのできない、クリニックの裏側や様々な医療機器を、間近にご覧になれるチャンスです。
近隣の方も、茅ヶ崎本院におかかりの方も、是非お誘いあわせの上お越しください!
(なお、3月21日には関係者様向けの内覧会を先行実施します。近隣の医療関係者の方やお取引先の業者様は、ご連絡は不要ですので是非とも3月21日にお越しください!)
そんな「平塚内科と呼吸のクリニック」では、茅ヶ崎本院同様、内科診療、呼吸器・アレルギー専門診療を一つの軸として診療を行いますが、もう一つの軸として、その抜群のアクセスを活かした、気軽に受けられる「予防医療」を掲げます。
つまり、「健康診断」「人間ドック」にも力を入れていく方針です。
その「人間ドック」に欠かせない検査といえば、「胃カメラ」「大腸カメラ」です。
「胃カメラ」「大腸カメラ」と聞くと、「苦しそう」「怖い」「できれば受けたくない」と感じる方は少なくないようです。
実際に、人間ドックで勧められても迷ってしまったり、症状があっても我慢してしまったりする方は少なくありません。
しかし、胃カメラや大腸カメラは、私たちの体の中で起きている変化を早く見つけ、健康を守るためにとても大切な検査なのです。
症状がないうちから「胃カメラ」「大腸カメラ」を行う意義は、検査をしなければわからない早期の病気発見にあります。
胃や大腸の病気、特にがんは、初期の段階ではほとんど症状が出ないことが多いのが特徴です。
「特に不調はないから大丈夫」と思っていても、気づかないうちに病気が進んでいることもあります。
胃カメラや大腸カメラは、胃や腸の中を直接観察できるため、症状が出る前の小さな異常や、早い段階のがんや、将来がんに進んでしまうリスクのあるポリープを見つけることができる検査です。
早期に発見できれば、体への負担が少ない治療で済むことが多く、日常生活への影響も最小限に抑えられますし、なにより命に関わるほど進んでしまわないようにすることで、より充実した人生を送ることにつなぐことができるのです。
また、胃の痛みや重苦しさ、胸やけ、胃もたれといった胃の症状、下痢や便秘を繰り返す、便が細くなった、血便が出たといった大腸の症状、それに、食欲不振、体重減少などの全身症状は、忙しさやストレスのせいだと思って様子を見てしまったり、「一時的なものだから様子をみよう」と安易に後回しにしてしまう方が少なくありません。
しかし、こうした症状の背景には、胃では逆流性食道炎や胃炎、胃潰瘍、大腸では大腸ポリープ、大腸の炎症、それに胃がん、大腸がんなどが隠れていることがあります。
こういった症状が出た時に胃カメラや大腸カメラを行うことで、症状の原因をはっきりさせたり、あらかじめ予防的な処置をして病気の進行を食い止めるなど、適切な対策につなげることができます。
そして、胃カメラ、大腸カメラの大きなメリットの一つは、「安心できること」です。
検査を受けて異常がなければ、「大きな病気ではなかった」と分かり、気持ちが軽くなります。
症状の原因が分かることで、必要以上に不安を感じることもなくなります。
また、もし異常が見つかった場合でも、早い段階であれば治療の選択肢が広がり、結果として体への負担を減らすことができます。
最近では、検査の苦痛をできるだけ減らす工夫も進んでいます。
内視鏡も以前より細くてやわらかくなり、検査が楽になってきていますし、鎮静剤もより一般的になったことで、昔よりも検査がだいぶ楽になっています。
そんな皆さんの健康を守る「胃カメラ」「大腸カメラ」を、「平塚内科と呼吸のクリニック」では、より快適に受けて頂けるようにしたいと思っています。
今日は「胃カメラ」「大腸カメラ」をどのように運用するか、ヒントを得るために、(私の学生、研修医時代から友人の)「青葉台かなざわ内科・内視鏡クリニック」の金沢憲由先生に、新事務長となるO崎とともに、お勉強に伺いました。
左が金沢先生
いやあ、さすが内視鏡を極めているクリニックは流れがスムーズ・・・
患者さんも流れるように案内され、効率よい動線で苦痛なく検査を受けられ帰る姿が印象的でした。
O崎とともに院内のいろんなところをチェックさせてもらって、頭に叩き込んできました。

この知見を活かして、患者さんに気持ちよく検査を受けて頂ける体制を整えていきたいと思っています!
※なお、検査の集約を行うため、長年行ってきた茅ヶ崎内科と呼吸のクリニックでの胃カメラ検査は、この2月をもって終了とさせて頂きます。
長い間のご愛顧、誠にありがとうございました。
茅ヶ崎市の検診は今後行うことは出来ませんが、健康診断や経過観察、それに胃腸症状があった際の胃カメラ検査は、平塚内科と呼吸のクリニックにダイレクトにおつなぎする体制を取る予定です。
改札からスグで、麻酔をしてもカンタンに車を使わずに帰れる「平塚内科と呼吸のクリニック」での検査を是非ご利用ください!