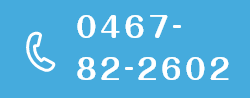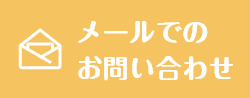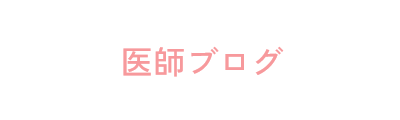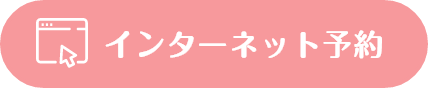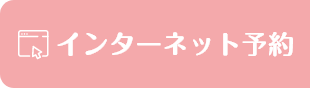・Homeostasis model assessment-(insulin)resistance HOMA-R
ーインスリン抵抗性を簡便に評価する方法
ーHOMA-R=空腹時血糖値(FBS) mg/dl × 空腹時インスリン値(FIRI )micU/ml/405
・正常 1.6以下 インスリン抵抗性あり 2.5以上
・HOMA-Rの上昇と中性脂肪はよく相関する
-空腹時のTG上昇は、インスリン抵抗性を示唆する
・HOMAーRが2.5未満であってもインスリン抵抗性が存在することが多く、1.6未満であってもインスリン抵抗 性が存在することが多い。
・FBSが140以下の場合はインスリン抵抗性の良い指標(血糖上昇に対して、インスリン分泌が直線的に増加 することが前提であり、糖尿病のようにインスリンの追随が頭打ちになってくると相関を示さない。)
・肥満例ではインスリンの追随が良好であり、相関が良好、非肥満例では良好な相関はみとめられない。
・早朝空腹時の血中インスリンの値が15μU/ml以上の場合には明らかなインスリン抵抗性がある .
HOMA-β
・HOMA-β(%)=(空腹時インスリン値(FIRI )×360)/(空腹時血糖値(FBS)-63)
・膵β細胞のインスリン分泌能を示した指標
・正常値40~60、それ以下ではインスリン分泌能低下
c-peptide値
・インスリン分泌量の測定する検査。
C-ペプチド(CPR)は、分泌刺激により、インスリンと共に膵臓β細胞から血中に放出される。C-ペプチドはインスリンとくっついた状態で分泌されるので、内因性インスリン分泌の評価や糖尿病の病型判定のためにおこなうのに適している。
・膵臓では、プロインスリンという物質が分解してインスリンが作られる過程で、C-ペプチドが生じる。このうち一定部分が尿中に排泄されるのでインスリンの分泌能がわかる
・インスリン療法を行っているかたの膵臓の働きをみるのに適する
インスリンの場合、糖尿病の人は血糖を下げるために皮下にインスリン注射をして注入するため、これの量も測定されてしまうから、自分の膵臓でどれだけ分泌しているのかわからない。C-ペプチドを測定すれば自分の力でどれだけ分泌できているかわかります。
C-ペプチドを測定して自分の力でインスリンが十分分泌されていることがわかれば、インスリン注射をやめることもできます。そのためにC-ペプチドを測定します。
基準値
インスリン(IRI)5~15μU/mL
C-ペプチド血中:1.2~2ng/mL 尿中:40~100μg/day
2010.12.15更新
セミナー復習3 1,5-anhydro-D-glucitol(1,5-AG)2010-12-15
1,5-anhydro-D-glucitol(1,5-AG)
・HbA1cやGAなどの糖化タンパクと異なり、グルコースに類似した構造をもつ生体内ポリオールのひとつ
・肝におけるグリコーゲン分解時に生成されることから、グリコーゲン代謝を司るセンサーとしての役割が示唆される
・生体内1,5AGの90%は食物由来であり腎糸球体でろ過されたのちほとんどが尿細管で再吸収され、通常
はほぼ一定の値を示す。
・高血糖時の尿等が陽性時には、尿細管での再吸収が阻害され尿中排泄が増加し、血中濃度は低下する。
1,5AGの臨床的意義
・尿中排泄量を反映する。
・数日間の短期血糖コントロール指標として利用される
・HbA1c>8%などのコントロール不良な糖尿病では。極端な低値を示すため臨床的な意味が低くなる。
・血糖の日内変動の大きさや食後高血糖を反映するため臨床上の有用性は大きい
・偽低値
腎性糖尿、妊娠30週以降、慢性腎不全、飢餓、重症肝疾患、
αグルコしダーゼ阻害薬使用中
・偽高値
人参栄養湯、加味帰脾湯服用時(大量の1.5AGが含まれる)
・HbA1cやGAなどの糖化タンパクと異なり、グルコースに類似した構造をもつ生体内ポリオールのひとつ
・肝におけるグリコーゲン分解時に生成されることから、グリコーゲン代謝を司るセンサーとしての役割が示唆される
・生体内1,5AGの90%は食物由来であり腎糸球体でろ過されたのちほとんどが尿細管で再吸収され、通常
はほぼ一定の値を示す。
・高血糖時の尿等が陽性時には、尿細管での再吸収が阻害され尿中排泄が増加し、血中濃度は低下する。
1,5AGの臨床的意義
・尿中排泄量を反映する。
・数日間の短期血糖コントロール指標として利用される
・HbA1c>8%などのコントロール不良な糖尿病では。極端な低値を示すため臨床的な意味が低くなる。
・血糖の日内変動の大きさや食後高血糖を反映するため臨床上の有用性は大きい
・偽低値
腎性糖尿、妊娠30週以降、慢性腎不全、飢餓、重症肝疾患、
αグルコしダーゼ阻害薬使用中
・偽高値
人参栄養湯、加味帰脾湯服用時(大量の1.5AGが含まれる)
投稿者:
2010.12.14更新
セミナー復習2 HbA1c 、グルコアルブミン GA 2010-12-14
HbA1C
・ヘモグロビンAのΒ鎖N末端のバリンにグルコースが非酵素的に結合(グリケーション)したもの
-グルコースは液相(血液中など)では、常に一定の割合でタンパク質と結合する
-もとのタンパク質の機能を阻害する
・過去1~2ヶ月の平均を反映 血糖の上下が激しい場合は反映されない
・偽高値
アルコール多飲、大量のビタミンC、高ビリルビン血症
・偽低値
溶血亢進、肝硬変、鉄欠乏性貧血の回復期、EPOによる貧血治療中、出血後、妊娠
グルコアルブミン GA
・グルコースとアルブミンが非酵素的に結合したもの
アルブミンはグリケーションされやすいため食後高血糖はHbA1cより反映される
・過去2~4週間の血糖の平均を反映
-アルブミンの半減期は20日でヘモグロビンより短い
・偽高値
肝硬変、甲状腺機能低下症、栄養障害
アルブミン半減期が延長する場合
・偽低値
ネフローゼ症候群、甲状腺機能亢進症、火傷
アルブミン半減期が短縮する場合
HbA1cとGAについて
・多くの臨床研究や診断基準がHbA1cであるため、HbA1c測定が一般化されている。
・GAは、その構造上の特徴や半減期などからHbA1cよりも血糖の変化にたいして早く、大きく変動することから臨床的な意義は大きいものと思われる。
-糖尿病の治療効果の早期判定に有用
-HbA1cの偽高値、偽低値を示す不適切な場合も有用
・血糖が安定している状況下では、GAはHbA1cの約3倍といわれている
HbA1c、GAの問題点
・相関回帰式から理論値の土20%以上乖離する例が全体の10%いじょうある
・合併症を有する症例、血糖の日内変動が激しい例では乖離が高い
-日内変動上昇によりGA/HbA1c比が高値となり実際の血糖コントロールよりもHbA1cが低くなる
*HbA1cは、食後高血糖を反映しない
GAを測定すべき病態
・不安定型糖尿病
・糖尿病の治療早期
・糖尿病の急性増悪によるコントロール評価
・妊娠糖尿病
・血液透析
・肝硬変、重度肝疾患
・HbA1cの偽高値、偽低値を示す疾患
・血糖とHbA1cの乖離があるとき
・ヘモグロビンAのΒ鎖N末端のバリンにグルコースが非酵素的に結合(グリケーション)したもの
-グルコースは液相(血液中など)では、常に一定の割合でタンパク質と結合する
-もとのタンパク質の機能を阻害する
・過去1~2ヶ月の平均を反映 血糖の上下が激しい場合は反映されない
・偽高値
アルコール多飲、大量のビタミンC、高ビリルビン血症
・偽低値
溶血亢進、肝硬変、鉄欠乏性貧血の回復期、EPOによる貧血治療中、出血後、妊娠
グルコアルブミン GA
・グルコースとアルブミンが非酵素的に結合したもの
アルブミンはグリケーションされやすいため食後高血糖はHbA1cより反映される
・過去2~4週間の血糖の平均を反映
-アルブミンの半減期は20日でヘモグロビンより短い
・偽高値
肝硬変、甲状腺機能低下症、栄養障害
アルブミン半減期が延長する場合
・偽低値
ネフローゼ症候群、甲状腺機能亢進症、火傷
アルブミン半減期が短縮する場合
HbA1cとGAについて
・多くの臨床研究や診断基準がHbA1cであるため、HbA1c測定が一般化されている。
・GAは、その構造上の特徴や半減期などからHbA1cよりも血糖の変化にたいして早く、大きく変動することから臨床的な意義は大きいものと思われる。
-糖尿病の治療効果の早期判定に有用
-HbA1cの偽高値、偽低値を示す不適切な場合も有用
・血糖が安定している状況下では、GAはHbA1cの約3倍といわれている
HbA1c、GAの問題点
・相関回帰式から理論値の土20%以上乖離する例が全体の10%いじょうある
・合併症を有する症例、血糖の日内変動が激しい例では乖離が高い
-日内変動上昇によりGA/HbA1c比が高値となり実際の血糖コントロールよりもHbA1cが低くなる
*HbA1cは、食後高血糖を反映しない
GAを測定すべき病態
・不安定型糖尿病
・糖尿病の治療早期
・糖尿病の急性増悪によるコントロール評価
・妊娠糖尿病
・血液透析
・肝硬変、重度肝疾患
・HbA1cの偽高値、偽低値を示す疾患
・血糖とHbA1cの乖離があるとき
投稿者:
2010.12.13更新
セミナー復習1 糖化:glycation 2010-12-13
今日から先日のセミナーの復習をします。
糖化反応(glycation)
・グルコースなどの還元糖とたんぱく質との非酵素的な結合
その代表的な生成物としてヘモグロビンA1c(HbA1c)、グリコアルブミン(GA)が血糖コントロール指標として糖尿病治療領域で臨床応用。 アルブミンとヘモグロビンと比較するとglycationが10倍アルブミンがおこしやすいためGAのほうが感度が高いため、食後高血糖はHbACより反映される。
・食品化学の分野では、食品の褐変減少として知られておりメイラード反応と呼ばれている。(1912年にLC Maillardがアミノ酸と還元糖を加熱すると褐色の色素が生成することを発見したことから、メイラード反応として知られるようになった)
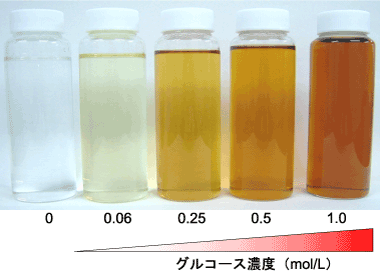
糖化反応のモデル実験
・糖化反応は、グルコース濃度に依存しして起こり、生体の蛋白に影響を与える。
・糖化反応は、アマドリ化合物形成に至る初期段階と後期反応性生物(advanced glycation endproduct:
AGE)に至る後期段階に分けてかんがえられる。
glycation反応経路
アミノ基(たんぱく質) + カルボニル基(グルコース/フルクトース)
↓ ↑
シッフ塩基化合物(アルジミン)
初期反応 ↓
↑
-------- アマドリ化合物(ケトアミン)
↓
後期反応 ↓
AGE受容体
後期反応性生成物 → AGE・ペプチド
(advanced glycation endproduct)
細胞はAGE修飾タンパクとAGE受容体の結合を引き金にして、サイトカインや成長因子の産生亢進など種々の細胞応答を引き起こし、糖尿病血管合併症をはじめとする種々の疾患発症・進展へと向かうことが考えられている。AGE修飾タンパクが糖尿病性血管合併症、動脈硬化、アルツハイマー病など、多くの疾患病変部に沈着していることが確認された。これら病変部でのAGEs蓄積が、その病気の直接因子なのか、単に病態の結果を反映しているのかは今もなお明確になっていないが、多くの研究がAGE受容体との反応が病変の発症・進展に必須な役割を果たしているという視点から展開している。
糖化反応(glycation)
・グルコースなどの還元糖とたんぱく質との非酵素的な結合
その代表的な生成物としてヘモグロビンA1c(HbA1c)、グリコアルブミン(GA)が血糖コントロール指標として糖尿病治療領域で臨床応用。 アルブミンとヘモグロビンと比較するとglycationが10倍アルブミンがおこしやすいためGAのほうが感度が高いため、食後高血糖はHbACより反映される。
・食品化学の分野では、食品の褐変減少として知られておりメイラード反応と呼ばれている。(1912年にLC Maillardがアミノ酸と還元糖を加熱すると褐色の色素が生成することを発見したことから、メイラード反応として知られるようになった)
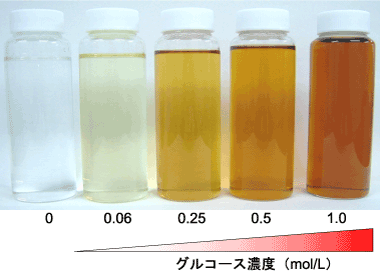
糖化反応のモデル実験
・糖化反応は、グルコース濃度に依存しして起こり、生体の蛋白に影響を与える。
・糖化反応は、アマドリ化合物形成に至る初期段階と後期反応性生物(advanced glycation endproduct:
AGE)に至る後期段階に分けてかんがえられる。
glycation反応経路
アミノ基(たんぱく質) + カルボニル基(グルコース/フルクトース)
↓ ↑
シッフ塩基化合物(アルジミン)
初期反応 ↓
↑
-------- アマドリ化合物(ケトアミン)
↓
後期反応 ↓
AGE受容体
後期反応性生成物 → AGE・ペプチド
(advanced glycation endproduct)
細胞はAGE修飾タンパクとAGE受容体の結合を引き金にして、サイトカインや成長因子の産生亢進など種々の細胞応答を引き起こし、糖尿病血管合併症をはじめとする種々の疾患発症・進展へと向かうことが考えられている。AGE修飾タンパクが糖尿病性血管合併症、動脈硬化、アルツハイマー病など、多くの疾患病変部に沈着していることが確認された。これら病変部でのAGEs蓄積が、その病気の直接因子なのか、単に病態の結果を反映しているのかは今もなお明確になっていないが、多くの研究がAGE受容体との反応が病変の発症・進展に必須な役割を果たしているという視点から展開している。
投稿者:
2010.12.13更新
セミナー復習1 糖化:glycation 2010-12-13
今日から先日のセミナーの復習をします。
糖化反応(glycation)
・グルコースなどの還元糖とたんぱく質との非酵素的な結合
その代表的な生成物としてヘモグロビンA1c(HbA1c)、グリコアルブミン(GA)が血糖コントロール指標として糖尿病治療領域で臨床応用。 アルブミンとヘモグロビンと比較するとglycationが10倍アルブミンがおこしやすいためGAのほうが感度が高いため、食後高血糖はHbACより反映される。
・食品化学の分野では、食品の褐変減少として知られておりメイラード反応と呼ばれている。(1912年にLC Maillardがアミノ酸と還元糖を加熱すると褐色の色素が生成することを発見したことから、メイラード反応として知られるようになった)
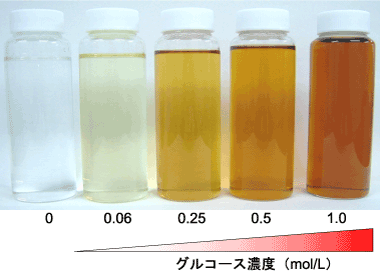
・糖化反応は、グルコース濃度に依存しして起こり、生体の蛋白に影響を与える。
・糖化反応は、アマドリ化合物形成に至る初期段階と後期反応性生物(advanced glycation endproduct:
AGE)に至る後期段階に分けてかんがえられる。
glycation反応経路
アミノ基(たんぱく質) + カルボニル基(グルコース/フルクトース)
↓ ↑
シッフ塩基化合物(アルジミン)
初期反応 ↓
↑
-------- アマドリ化合物(ケトアミン)
↓
後期反応 ↓
AGE受容体
後期反応性生成物 → AGE・ペプチド
(advanced glycation endproduct)
細胞はAGE修飾タンパクとAGE受容体の結合を引き金にして、サイトカインや成長因子の産生亢進など種々の細胞応答を引き起こし、糖尿病血管合併症をはじめとする種々の疾患発症・進展へと向かうことが考えられている。AGE修飾タンパクが糖尿病性血管合併症、動脈硬化、アルツハイマー病など、多くの疾患病変部に沈着していることが確認された。これら病変部でのAGEs蓄積が、その病気の直接因子なのか、単に病態の結果を反映しているのかは今もなお明確になっていないが、多くの研究がAGE受容体との反応が病変の発症・進展に必須な役割を果たしているという視点から展開している。
糖化反応(glycation)
・グルコースなどの還元糖とたんぱく質との非酵素的な結合
その代表的な生成物としてヘモグロビンA1c(HbA1c)、グリコアルブミン(GA)が血糖コントロール指標として糖尿病治療領域で臨床応用。 アルブミンとヘモグロビンと比較するとglycationが10倍アルブミンがおこしやすいためGAのほうが感度が高いため、食後高血糖はHbACより反映される。
・食品化学の分野では、食品の褐変減少として知られておりメイラード反応と呼ばれている。(1912年にLC Maillardがアミノ酸と還元糖を加熱すると褐色の色素が生成することを発見したことから、メイラード反応として知られるようになった)
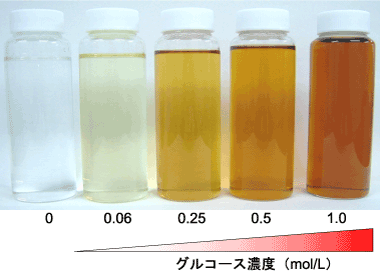
・糖化反応は、グルコース濃度に依存しして起こり、生体の蛋白に影響を与える。
・糖化反応は、アマドリ化合物形成に至る初期段階と後期反応性生物(advanced glycation endproduct:
AGE)に至る後期段階に分けてかんがえられる。
glycation反応経路
アミノ基(たんぱく質) + カルボニル基(グルコース/フルクトース)
↓ ↑
シッフ塩基化合物(アルジミン)
初期反応 ↓
↑
-------- アマドリ化合物(ケトアミン)
↓
後期反応 ↓
AGE受容体
後期反応性生成物 → AGE・ペプチド
(advanced glycation endproduct)
細胞はAGE修飾タンパクとAGE受容体の結合を引き金にして、サイトカインや成長因子の産生亢進など種々の細胞応答を引き起こし、糖尿病血管合併症をはじめとする種々の疾患発症・進展へと向かうことが考えられている。AGE修飾タンパクが糖尿病性血管合併症、動脈硬化、アルツハイマー病など、多くの疾患病変部に沈着していることが確認された。これら病変部でのAGEs蓄積が、その病気の直接因子なのか、単に病態の結果を反映しているのかは今もなお明確になっていないが、多くの研究がAGE受容体との反応が病変の発症・進展に必須な役割を果たしているという視点から展開している。
投稿者:
2010.12.12更新
1dayセミナー アドバンス 2010-12-12
mssの1dayセミナー アドバンスを受講してきました。
これは分子整合栄養学のセミナーで、新宿溝口クリニックの溝口先生が実際の症例の検査データを提示されそれより不足栄養素を考え結果がどうなったか詳細な説明をするものです。小生にとっては、やや高度な内容でしたが、糖尿病の食事、インスリン、糖化glycation、Hba1cとグリコアルブミン、HOMA-R、コレステロールの話と多岐にわたっていましたが、興味深く拝聴しました。
来年は基礎編より勉強しなおさなければと思い来年のセミナーも申し込みすることにしました。
これは分子整合栄養学のセミナーで、新宿溝口クリニックの溝口先生が実際の症例の検査データを提示されそれより不足栄養素を考え結果がどうなったか詳細な説明をするものです。小生にとっては、やや高度な内容でしたが、糖尿病の食事、インスリン、糖化glycation、Hba1cとグリコアルブミン、HOMA-R、コレステロールの話と多岐にわたっていましたが、興味深く拝聴しました。
来年は基礎編より勉強しなおさなければと思い来年のセミナーも申し込みすることにしました。
投稿者:
2010.12.11更新
ナースのための褥瘡超音波検査 2010-12-11
ナースのための褥瘡超音波検査(アスリードセミナー)に参加してきました。
褥瘡と超音波検査、私の知識の中では今まで関連がないものと思っていました。タイトル名に興味をおぼえ参加しました。東葛クリニック病院の富田則明先生の講演で使用した機種は携帯型エコーのnanomaxxという装置でした。この装置は以前ソノサイトという名前でオリンパスが販売していたものの改良されたものとのことです。
前般は超音波の基礎的な講義とプローブの握り方、走査法のハンズオンで後半は褥瘡の原因、NPUAPのSTAGE分類、DTI(Deep Tissue injury)、褥瘡の超音波所見を中心に症例を供覧していただきました。
超音波検査を取り入れることにより
1.DTIを早期に判断でき予防ケアの充実化を図れる
2.褥瘡の急性期 介入初日でも変化の過程を予測でき治療方針やケア目標が立案
3.予防ケアの評価が客観的にわかる
褥瘡はチーム医療として患者の状況に的確に対応した医療を提供することが大事とのことでした。
明日は分子整合栄養学の1dayセミナーに行ってきます。
褥瘡と超音波検査、私の知識の中では今まで関連がないものと思っていました。タイトル名に興味をおぼえ参加しました。東葛クリニック病院の富田則明先生の講演で使用した機種は携帯型エコーのnanomaxxという装置でした。この装置は以前ソノサイトという名前でオリンパスが販売していたものの改良されたものとのことです。
前般は超音波の基礎的な講義とプローブの握り方、走査法のハンズオンで後半は褥瘡の原因、NPUAPのSTAGE分類、DTI(Deep Tissue injury)、褥瘡の超音波所見を中心に症例を供覧していただきました。
超音波検査を取り入れることにより
1.DTIを早期に判断でき予防ケアの充実化を図れる
2.褥瘡の急性期 介入初日でも変化の過程を予測でき治療方針やケア目標が立案
3.予防ケアの評価が客観的にわかる
褥瘡はチーム医療として患者の状況に的確に対応した医療を提供することが大事とのことでした。
明日は分子整合栄養学の1dayセミナーに行ってきます。
投稿者:
ARTICLE
SEARCH
ARCHIVE
- 2025年12月 (2)
- 2025年11月 (2)
- 2025年10月 (2)
- 2025年09月 (2)
- 2025年08月 (2)
- 2025年07月 (2)
- 2025年06月 (1)
- 2025年05月 (2)
- 2025年04月 (2)
- 2025年03月 (1)
- 2025年02月 (2)
- 2025年01月 (2)
- 2024年12月 (2)
- 2024年11月 (1)
- 2024年10月 (1)
- 2024年09月 (3)
- 2024年08月 (2)
- 2024年07月 (2)
- 2024年06月 (2)
- 2024年05月 (1)
- 2024年04月 (1)
- 2024年03月 (2)
- 2024年02月 (1)
- 2024年01月 (2)
- 2023年12月 (2)
- 2023年11月 (1)
- 2023年10月 (1)
- 2023年09月 (1)
- 2023年08月 (2)
- 2023年07月 (1)
- 2023年06月 (1)
- 2023年05月 (2)
- 2023年04月 (1)
- 2023年03月 (2)
- 2023年02月 (1)
- 2023年01月 (1)
- 2022年12月 (2)
- 2022年11月 (1)
- 2022年10月 (1)
- 2022年09月 (1)
- 2022年08月 (3)
- 2022年07月 (2)
- 2022年06月 (1)
- 2022年05月 (2)
- 2022年04月 (2)
- 2022年03月 (2)
- 2022年02月 (1)
- 2022年01月 (2)
- 2021年12月 (2)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (1)
- 2021年09月 (2)
- 2021年08月 (1)
- 2021年07月 (1)
- 2021年06月 (2)
- 2021年05月 (2)
- 2021年04月 (2)
- 2021年03月 (2)
- 2021年02月 (2)
- 2021年01月 (2)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (2)
- 2020年10月 (1)
- 2020年09月 (2)
- 2020年08月 (2)
- 2020年07月 (3)
- 2020年06月 (3)
- 2020年05月 (3)
- 2020年04月 (3)
- 2020年03月 (4)
- 2020年02月 (3)
- 2020年01月 (2)
- 2019年12月 (3)
- 2019年11月 (3)
- 2019年10月 (2)
- 2019年09月 (3)
- 2019年08月 (2)
- 2019年07月 (2)
- 2019年06月 (3)
- 2019年05月 (2)
- 2019年04月 (4)
- 2013年02月 (5)
- 2013年01月 (10)
- 2012年12月 (5)
- 2012年11月 (3)
- 2012年10月 (1)
- 2012年06月 (2)
- 2012年04月 (1)
- 2012年01月 (1)
- 2011年12月 (2)
- 2011年11月 (1)
- 2011年10月 (4)
- 2011年09月 (4)
- 2011年06月 (4)
- 2011年05月 (1)
- 2011年04月 (1)
- 2011年03月 (2)
- 2011年02月 (6)
- 2011年01月 (1)
- 2010年12月 (7)
- 2010年11月 (2)
- 2010年10月 (7)
- 2010年09月 (6)
- 2010年08月 (3)
- 2010年07月 (3)