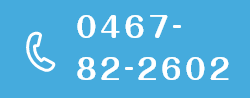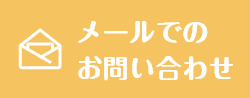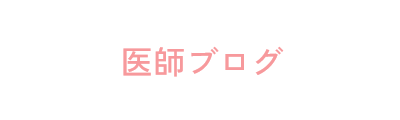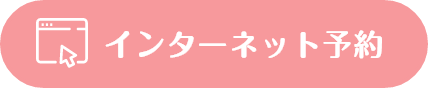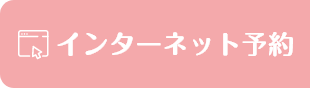糖化反応(glycation)
・グルコースなどの還元糖とたんぱく質との非酵素的な結合
その代表的な生成物としてヘモグロビンA1c(HbA1c)、グリコアルブミン(GA)が血糖コントロール指標として糖尿病治療領域で臨床応用。 アルブミンとヘモグロビンと比較するとglycationが10倍アルブミンがおこしやすいためGAのほうが感度が高いため、食後高血糖はHbACより反映される。
・食品化学の分野では、食品の褐変減少として知られておりメイラード反応と呼ばれている。(1912年にLC Maillardがアミノ酸と還元糖を加熱すると褐色の色素が生成することを発見したことから、メイラード反応として知られるようになった)
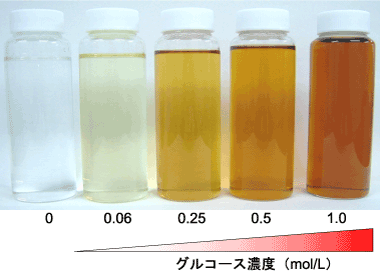
・糖化反応は、グルコース濃度に依存しして起こり、生体の蛋白に影響を与える。
・糖化反応は、アマドリ化合物形成に至る初期段階と後期反応性生物(advanced glycation endproduct:
AGE)に至る後期段階に分けてかんがえられる。
glycation反応経路
アミノ基(たんぱく質) + カルボニル基(グルコース/フルクトース)
↓ ↑
シッフ塩基化合物(アルジミン)
初期反応 ↓
↑
-------- アマドリ化合物(ケトアミン)
↓
後期反応 ↓
AGE受容体
後期反応性生成物 → AGE・ペプチド
(advanced glycation endproduct)
細胞はAGE修飾タンパクとAGE受容体の結合を引き金にして、サイトカインや成長因子の産生亢進など種々の細胞応答を引き起こし、糖尿病血管合併症をはじめとする種々の疾患発症・進展へと向かうことが考えられている。AGE修飾タンパクが糖尿病性血管合併症、動脈硬化、アルツハイマー病など、多くの疾患病変部に沈着していることが確認された。これら病変部でのAGEs蓄積が、その病気の直接因子なのか、単に病態の結果を反映しているのかは今もなお明確になっていないが、多くの研究がAGE受容体との反応が病変の発症・進展に必須な役割を果たしているという視点から展開している。